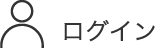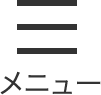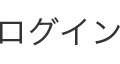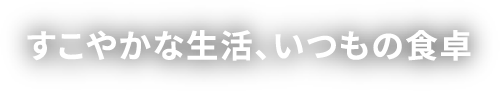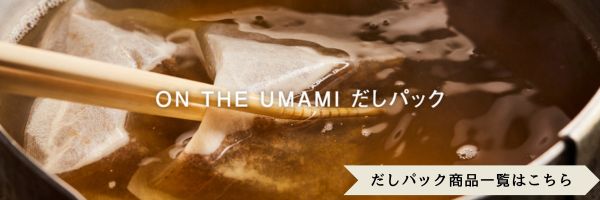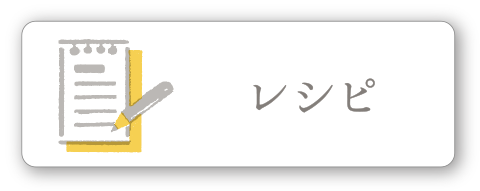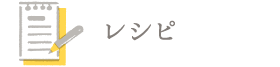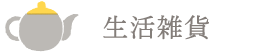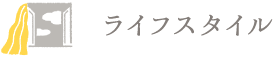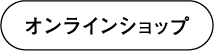日本の地域による出汁の違いとは?歴史と文化を紐解く

日本の食卓を彩る、かけがえのない存在「出汁」。
その奥深い世界には、地域によって驚くほど異なる文化が息づいています。
同じ「かつおだし」でも、関東と関西では色や風味に違いがあることをご存知でしょうか。
実は、その違いは、歴史や地理、そして人々の暮らしと深く関わっているのです。
今回は、日本の地域による出汁の違いとその背景を探り、その魅力に迫ります。
地域ごとの特徴を理解することで、料理の幅も大きく広がるはずです。
出汁の地域差と歴史
関東と関西の出汁文化
関東の出汁は、濃い色合いで、しっかりとしたコクのある味わいが特徴です。
一方、関西の出汁は、色が薄く、上品で繊細な風味です。
この違いは、使用する醤油や主材料の違い、そして歴史的・地理的背景に起因します。
関東では濃口醤油を使い、かつお節を主材料とする濃厚な出汁が好まれ、関西では薄口醤油を使い、昆布とかつお節を合わせた合わせだしが好まれます。
醤油の種類と材料の違い
関東では色が濃く、塩分とコクが強い濃口醤油が主流です。
そのため、出汁にも醤油の味が強く反映され、濃いめの味付けになります。
一方、関西では色が薄く、まろやかな味わいの薄口醤油が好まれます。
出汁では、醤油はあくまで風味付けとして使用され、素材本来の味を引き立てる役割を担います。
歴史的背景と地理的要因
関東の出汁文化は、江戸時代の町人文化と深く結びついています。
江戸は人口が多く、肉体労働者も多かったため、塩分を多く含む濃い味の料理が好まれたと考えられています。
また、北海道からの昆布の輸送が難しかったことも、かつお節中心の文化が形成された要因の一つです。
一方、関西では、京都の公家文化の影響が大きく、素材本来の味を生かす薄味の料理が発展しました。
良質な昆布が比較的容易に入手できたことも、昆布だしが中心となった理由でしょう。
関西の水質が軟水であることも、昆布だしが美味しくとれる要因の一つとして挙げられます。
全国各地の出汁文化の深掘り
地域ごとの主要材料
北海道では昆布、かつお節、煮干しなど多様な材料が使われます。
東北地方では煮干し、さば節などが中心です。
関東ではかつお節、さば節、昆布、煮干しなどが使われ、用途によって使い分けられています。
中部地方ではさば節、むろあじ節などが好まれます。
関西では昆布とかつお節の合わせだしが基本ですが、さば節や煮干しなども使われます。
中国・四国地方では煮干し、焼きあご(トビウオ)などが使われ、九州地方でも煮干し、焼きあごなどが中心です。
沖縄ではかつお節と昆布が広く使われています。
各地域の伝統と歴史
各地域の気候や風土、歴史、そして水産資源の豊かさなどが、それぞれの出汁文化を形作ってきました。
例えば、黒潮の影響でイワシが豊富に獲れる九州・四国地方では、煮干しが古くから使われてきました。
また、江戸時代、かつお節や昆布が高価だったため、安価な煮干しが広く普及した歴史もあります。
一方、京都を中心とした関西地方では、精進料理の伝統から、素材本来の味を生かす薄味の文化が発展し、昆布だしが中心となりました。
まとめ
日本の出汁文化は、地域によって大きく異なる多様な文化です。
その違いは、歴史、地理、そして人々の生活様式と深く関わっています。
関東のかつお節中心の濃厚な出汁、関西の昆布と合わせだしによる繊細な出汁、そして全国各地の個性豊かな出汁は、日本の食文化の豊かさを象徴しています。
それぞれの地域の出汁の特徴を理解することで、料理の奥深さ、そして日本の食文化への理解がさらに深まるでしょう。
ON THE UMAMIでは、出汁がもたらす旨味を日本人の本質的な感性であり、日本文化の礎として考えてます。
そんなON THE UMAMIが作る数々の出汁商品を通し、日本の食卓を彩る、出汁の世界をぜひ堪能してください。